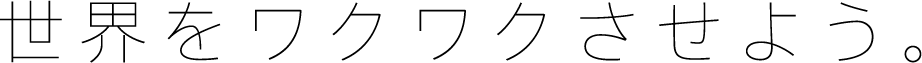「採用難が続く中、従来の採用手法だけでは優秀な人材の確保が難しい……」そんな悩みを抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
実は、自社の従業員から人材を紹介してもらう「リファーラル採用」なら、採用コストを抑えながら企業にマッチした人材を採用できる可能性があります。さらに、従業員のエンゲージメント向上にもつながるという副次的な効果も期待できます。
本記事では、リファーラル採用の基礎知識から、メリット・デメリット、成功のポイントまで徹底解説します。この記事を読めば、自社に最適なリファーラル採用の進め方が明確になるはずです。
目次
「リファーラル採用」とは?

リファーラル採用とは、自社の従業員から友人や知人を紹介してもらい、採用活動を行う手法です。「リファーラル(referral)」は「紹介・推薦」を意味し、欧米では一般的な採用手法として定着しています。
近年、少子高齢化による労働力人口の減少に伴い、従来の求人広告や人材紹介だけでは優秀な人材の確保が難しくなっています。リファーラル採用では、実際に働いている社員を通じて企業の魅力や仕事内容を生の声として伝えられることから、このような変化に対応できる採用手法として注目を集めています。
リファーラル採用の仕組み
リファーラル採用では、まず企業が募集している職種や求める人材像を社員に共有します。社員は自身のネットワークから適任者を見つけ、企業に紹介します。紹介された候補者は、通常の採用プロセスと同様に面接などの選考を受けることになります。
多くの企業では、採用が成功した場合、紹介者である社員にインセンティブを支給する制度を設けています。また、紹介者と候補者が会食する際の経費補助など、採用活動をサポートする制度を整備している企業も増えています。
「縁故採用」との違い
縁故採用は主に役員や幹部社員からの紹介による採用で、血縁・姻戚関係などの縁故を重視し、採用を前提に進められることが一般的です。そのため、面接や筆記試験などの選考プロセスが形式的になりがちで、スキルや適性よりも「コネ」が重視されるというネガティブなイメージがあります。
一方、リファーラル採用は全社員が紹介者となることができ、紹介後は通常の採用基準に基づいて選考が行われます。紹介者と候補者は対等な関係で、企業側も採用の可否を慎重に判断します。このため、よりオープンで公平な採用手法として認識されています。
リファーラル採用の実施例

日本企業におけるリファーラル採用の導入は、着実に広がりを見せています。大手通信企業、総合電機メーカー、金融系ウェブサービスなど、業界を問わず多くの企業が成果を上げています。
ここでは、国内のリファーラル採用を実施している企業の成功事例を紹介します。
大手通信企業
大手通信企業A社では、新しい採用方法としてリファーラル採用を取り入れ、目覚ましい成果を上げています。特に注目すべきは、リファーラル採用による応募から受諾に至る率が22%という高い数値を記録していることです。さらに、2019年8月以降に入社した社員の1年後の定着率は100%を達成しています。
A社の特徴的な取り組みは、管理職層からの紹介に重点を置いている点です。管理職以上が紹介した場合の入社率は4割以上と高い実績を残しています。また、採用が決定した際は紹介者である社員へインセンティブを支給していますが、金銭的な報酬以上に、採用部門のトップから現場への丁寧な価値浸透を重視しています。
大手総合電機メーカー
B社は、ICTサービス市場で国内トップクラスの実績を持つ企業です。先端技術を扱えるエンジニアの確保を目的にリファーラル採用を導入し、累計90名の採用に成功。その結果、1.2億円の採用コストの削減を実現しました。
特に専門性の高い技術を有する人材は転職市場に顕在化していないことから、従業員のネットワークを活用したアプローチを重視。リファーラル採用の認知度向上のため、説明機会の増加や入社者のインタビュー記事掲載など、積極的な情報発信を行っています。
金融系のウェブサービスを展開している企業
クラウド型の会計ソフトを提供するC社では、リファーラル採用を促進するため、ユニークな施策を展開しています。従業員が紹介したい候補者とともに社内で食事ができる制度を設けており、これにより候補者が会社の雰囲気をより深く理解できる機会を創出しています。
C社の特徴は、単なる紹介制度にとどまらず、候補者が企業文化を体感できる仕組みを整備している点です。こうした取り組みにより、入社後のミスマッチを防ぎ、採用効率の向上を実現しています。リファーラル採用による採用者は全体の約3割を占め、安定した採用成果を上げています。
リファーラル採用の費用

リファーラル採用は、求人広告費や人材紹介料といった外部コストを抑えられる採用手法として注目されています。しかし、効果的な運用のためには適切な予算配分と制度設計が必要です。
主な費用は以下の3つに分類されます。まず、紹介者へのインセンティブです。これは採用成功時の報酬として設定され、適切な金額設定が重要です。次に、採用活動に伴う必要経費です。候補者との面談費用や交通費など、実務的なコストをカバーします。最後に、運用効率を高めるためのツールや外部サービスの利用料です。
これらの費用は、従来の採用手法と比較すると総じて低コストとなりますが、企業規模や採用ニーズに応じて最適な予算配分を検討する必要があります。以下では、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。
紹介者へのインセンティブの目安
リファーラル採用での紹介者インセンティブは、3~10万円が最も一般的で、多くの企業が30万円以内に設定しています。
この報酬は、社員が優秀な候補者を紹介する動機付けになりますが、高額すぎると不適切な紹介が増えるリスクがあります。インセンティブは金銭だけでなく、従業員特典や体験型報酬も効果的です。公平で明確なルールを設け、モチベーションを持続させることが重要です。
採用活動費などの必要経費
リファーラル採用では、面談費や候補者との会食費用などが発生します。社員が候補者を誘いやすい環境を作るため、会食費の補助が有効です。
ただし、目的が単なる費用請求にならないよう、透明性の高いルール設定が不可欠です。タレントプールの活用や経費申請条件の明確化で、制度の質を向上させられます。
ツール・外部サービスの利用料金
リファーラル採用の効率化には、ツール導入が有効です。専用プラットフォームやSNSを活用することで、候補者紹介と管理が簡素化されます。
料金はサービスによりますが、長期的なコスト削減と採用成功率向上を考慮すると、導入の価値があります。選定時には機能や価格を比較し、自社ニーズに合うものを選びましょう。
リファーラル採用でよくあるトラブル

リファーラル採用は効率的で優秀な人材を獲得しやすい手法ですが、注意を怠るといくつかのトラブルが発生する可能性があります。特に人間関係の摩擦や法的リスクなどが挙げられます。これらのトラブルを未然に防ぐためには、適切な制度設計と透明性のある採用フローの構築が欠かせません。
以下では、リファーラル採用における代表的な課題である「人間関係の悪化」と「法律違反のリスク」について解説し、それぞれの対策方法をご紹介します。
人間関係が悪化することがある
リファーラル採用では、紹介者と被紹介者間の関係性が業務に影響を及ぼすことがあります。不採用時に紹介者が不満を抱いたり、紹介された側が紹介者に対して不信感を持ったりするケースも考えられます。また、採用後にグループ化や特定の派閥形成が進むと、社内の一体感が損なわれる恐れがあります。
このようなリスクを回避するには、制度設計の段階でトラブル回避の工夫をすることが重要です。例えば、不採用時の丁寧な説明プロセスを設けたり、紹介者と被紹介者の評価を独立して行う仕組みを導入したりすることが効果的です。さらに、社内のオープンなコミュニケーション文化を育むことで、潜在的な摩擦を減らすことができます。
法律を違反することがある
リファーラル採用において、特に注意が必要なのは職業安定法に関する法的リスクです。紹介者へのインセンティブは、職業安定法第30条に基づき、適切に設計する必要があります。高額すぎるインセンティブは、人材紹介事業とみなされる可能性があり、法律違反となる恐れがあります。
インセンティブを設定する際は、通常の業務の一環として「給与やそれに準ずるもの」として位置づけ、就業規則や雇用契約書に明記することが重要です。また、紹介活動に関する経費や時間外労働の取り扱いなども明確にルール化し、労働基準法に則った運用を心がける必要があります。
法令順守の観点から、インセンティブの金額は人材紹介会社への紹介料よりも低く設定することが推奨されます。
リファーラル採用を導入するメリット

リファーラル採用は、従来の採用手法と比べて効率的でコストパフォーマンスが高く、企業に多くの利点をもたらします。その特徴は、転職活動をしていない優秀な人材にアプローチできる点や、社員の紹介を通じて企業と候補者の相性が良くなりやすい点です。また、採用コストの削減や入社後の離職率低下といった成果も期待できます。
以下では、リファーラル採用の具体的なメリットを4つの観点から詳しく解説します。
転職活動していない人材と接点が持てる
リファーラル採用の大きな特徴は、転職サイトや人材紹介会社を通じた一般的な採用では出会えない人材との接点を持てることです。現在転職を考えていない優秀な人材でも、信頼できる知人からの紹介であれば、興味を持って話を聞いてくれる可能性が高くなります。
実際の職場で活躍している社員からの紹介は、求人広告よりも説得力があり、「あの人が働いているなら話を聞いてみよう」という関心を引き出すことができます。このように、潜在的な転職層へのアプローチが可能になることは、人材確保の選択肢を大きく広げることにつながります。
マッチングが取りやすい
リファーラル採用では、企業の理念や文化をよく理解している社員が紹介者となるため、企業との相性が良い人材を見極めやすいという特徴があります。紹介者は日々の業務や職場の雰囲気を熟知しているため、「この人なら自社で活躍できる」という視点で候補者を推薦してくれます。
また、候補者も紹介者から企業の詳しい情報を得られるため、入社前から仕事内容や職場環境について具体的なイメージを持つことができます。このように、双方向の理解が深まることで、採用時のミスマッチを大幅に減らすことが可能になります。
採用コストの削減になる
リファーラル採用では、求人広告の掲載料や人材紹介会社への手数料など、従来の採用手法で発生する主要なコストを削減できます。紹介者へのインセンティブは発生するものの、人材紹介会社の手数料と比較すると、大幅なコスト削減が可能です。
また、社員による事前のスクリーニング効果により、面接回数を削減できたり、採用プロセスを効率化できたりするため、採用にかかる人件費や時間的コストも抑制できます。これらの削減効果は、企業の採用予算の効率的な運用に貢献します。
離職率が低い
リファーラル採用による入社者は、一般的な採用ルートと比較して離職率が低い傾向にあります。これは、入社前に紹介者から仕事内容や職場の雰囲気について詳しい情報を得られるため、入社後のギャップが少ないことが要因です。
また、すでに社内に知人がいることで、業務上の不安や悩みを気軽に相談できる環境があり、スムーズな職場適応が期待できます。さらに、紹介者との信頼関係が基盤にあることで、早い段階から会社への帰属意識が芽生えやすいという特徴もあります。こうした要因により、長期的な人材定着が実現しやすくなります。
リファーラル採用を導入する際の注意点

リファーラル採用は、多くのメリットを持つ採用手法ですが、導入にはいくつかの課題も伴います。特に「人材の偏り」「大量採用への不向き」「情報の可視化不足」といった側面は、事前に対策を講じておかなければなりません。これらの課題を理解し、適切に補完する仕組みを取り入れることで、リファーラル採用を効果的に運用できます。
以下では、具体的な課題とその解決策について解説します。
人材が偏る可能性がある
リファーラル採用では、社員の人脈に基づいて候補者が選ばれるため、人材が特定の価値観や背景に偏るリスクがあります。同じような職務経験やスキルを持つ人が増える一方で、多様性が損なわれる可能性があります。
この課題を克服するには、採用基準を明確にし、特定のスキルや経験に限定しない広い視点で候補者を評価することが重要です。また、リファーラル採用以外の手法も併用して、幅広い候補者プールを確保することが推奨されます。さらに、バイアスを軽減するための採用ツールの導入も効果的です。
大量採用には向いていない
リファーラル採用は少人数の採用には高い効果を発揮しますが、大量採用には適していない場合があります。社員の人脈には限りがあり、一度に多くの候補者を集めることは困難です。そのため、事業拡大時や新規プロジェクトでの人員増加には課題が残ります。
この問題を解消するには、リファーラル採用を他の採用チャネルと組み合わせて運用する方法が有効です。例えば、大量採用時には求人広告やエージェントを活用しつつ、リファーラル採用を補助的に活用することで、質と量のバランスを保つことができます。
情報が可視化しにくい
リファーラル採用では、候補者情報や採用プロセスが社員任せになり、企業全体での可視化が難しくなる場合があります。これにより、採用状況を把握しづらく、最適な意思決定が行えないリスクが生じます。
この課題を解決するには、採用管理ツールの導入が効果的です。例えば、リファーラル専用のプラットフォームを使用することで、候補者情報や進捗状況を一元管理できます。また、定期的な報告や評価を行う仕組みを整備することで、透明性を向上させ、効率的な運用が可能になります。
リファーラル採用を実施する際のポイント

リファーラル採用を成功させるには、単に社員に紹介を依頼するだけではなく、制度の設計や運用まで細かく配慮する必要があります。具体的には、社員の参加意識を高める制度周知や、求める人材像の明確化、インセンティブ設計、他の採用チャネルとの連携が重要です。以下に、各ポイントについて詳しく解説します。
制度を社内で周知する
リファーラル採用を成功させるには、単に社員に紹介を依頼するだけではなく、制度の設計や運用まで細かく配慮する必要があります。
具体的には、社員の参加意識を高める制度周知や、求める人材像の明確化、インセンティブ設計、他の採用チャネルとの連携が重要です。以下に、各ポイントについて詳しく解説します。
求める人材像や基準を明確にする
リファーラル採用で適切な人材を確保するためには、求める人材像や採用基準を社員と共有する必要があります。
例えば、必要なスキルや経験、企業文化に合った特性などを明確にし、社内ネットワークや資料を活用して常に最新情報を更新・共有する仕組みを構築することが有効です。
紹介者へのインセンティブを決める
インセンティブは、社員の紹介意欲を高めるための重要な要素です。一般的には、3万円~10万円程度が主流であり、金銭的報酬だけでなく、体験型報酬や社内特典を活用する企業も増えています。
ただし、高額すぎる報酬はモチベーションの偏りや法令違反のリスクを招くため、適切な設定が求められます。
他のチャネルと合わせて実施する
リファーラル採用だけに依存するのではなく、求人広告やエージェントを併用することで、多様な人材プールを確保できます。
さらに、複数チャネルから集まる情報を一元管理することで、採用プロセスの効率化と人材の質の向上が期待されます。
社員に負荷をかけないようルールを整備する
社員が候補者を紹介しやすい環境を作るために、簡単な紹介フローを設定し、負担を最小限に抑える仕組みが必要です。
例えば、候補者情報を簡単に共有できるフォームの整備や、面談調整を人事部が担当する仕組みを導入することで、社員の負担を軽減できます。
社内イベントに招待する
候補者を社内イベントに招待することで、企業文化や職場の雰囲気を伝えることができます。これにより、応募者の興味を引き出し、選考前に相互理解を深めることが可能です。
このアプローチは、社員の紹介ハードルを下げる効果も期待できます。
リファーラル採用のサポートサービス
リファーラル採用をより効率的に運用するためには、専門のサポートサービスの活用が有効です。これらのサービスは、紹介プロセスの管理から情報の一元化、コミュニケーションの効率化まで、様々な機能を提供しています。
適切なサービスを選択し活用することで、運用負荷を軽減しながら、より効果的なリファーラル採用を実現できます。以下では、代表的なサービスについて詳しく解説していきましょう。
MyRefer(マイリファー)
MyReferは、2015年9月にリリースした国内初のリファーラル採用サービスで、1,000社以上の導入実績を誇ります。経験豊富なアドバイザーが蓄積されたノウハウをもとに、リファーラル採用の導入から運用までをトータルでサポートする点が特徴です。
主な機能としては、人事管理と告知機能、データ分析機能、退職者向け機能などがあり、SNS連携も可能です。特に、再雇用促進や転職潜在層の情報をプールする機能は、優秀な潜在層の獲得に有効です。また、オーダーメイド型の伴走サポートにより、企業の状況に応じた最適な運用を実現できます。
HERP Hire(ハープハイアー)
HERP Hireは、15社以上の求人媒体と連携し、社員が自律的に採用活動を行う「スクラム採用」を実現する採用管理プラットフォームです。1,500社以上の導入実績があり、特にIT系企業での活用が多いのが特徴です。
主な機能には、求人媒体からの応募情報自動連携、SlackやChatworkを通じた各種通知、潜在候補者のタレントプール管理、レポート分析機能などがあります。アカウント解説から利用開始後まで専任スタッフがサポートするため、スムーズな導入と運用が可能です。
まとめ
リファーラル採用は、企業の採用戦略において重要な選択肢となっています。人材獲得競争が激化する中、社員の人脈を活用することで、転職潜在層へのアプローチや採用コストの削減が可能になります。ただし、効果的な運用には適切な制度設計と全社的な理解が不可欠です。
リファーラル採用を導入し、社員と企業が一体となって取り組むことで、企業文化にマッチした優秀な人材を獲得し、持続的な組織の成長を実現することができます。