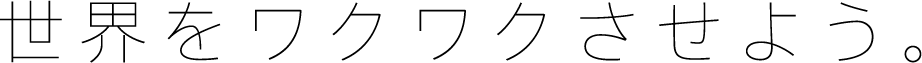採用戦略がうまくいかず悩んでいませんか?競争が激化する採用市場では、計画性と戦略が成功の鍵を握ります。採用戦略を適切に立てることで、優秀な人材の獲得やコスト削減が可能です。
本記事では、採用戦略の基礎から具体的な立案手順、成功事例までを網羅的に解説しています。読み終えた後には、自社に合った採用戦略を実行する自信と具体的な指針を得られるでしょう。これからの採用活動に新たな一歩を踏み出しましょう。
採用戦略とは?

企業の持続的な成長には、優秀な人材の確保が不可欠です。しかし、昨今の人口減少や少子高齢化により、人材獲得の競争は激化する一方です。そのため企業は、場当たり的な採用活動ではなく、戦略的なアプローチが求められています。ここでは、採用戦略の概要や背景、採用計画との違いについて解説します。
採用戦略とは
採用戦略とは、企業が求める人材を計画的かつ効果的に獲得するために立てる中長期的な計画です。単なる採用活動の指針ではなく、企業の経営計画や事業計画に基づいて策定される重要な経営戦略の一つです。
この背景には、深刻な労働人口の減少があります。2030年には644万人もの人手不足が予測されており、特に専門・技術人材の不足が顕著になると言われています。
また、求職者のニーズも多様化しており、給与や待遇だけでなく、働き方やキャリア形成、企業の社会的価値観なども重視されるようになっています。このような環境下で優秀な人材を確保するには、戦略的な採用活動が不可欠となっているのです。
採用戦略と採用計画の違い
採用計画は、「いつまでに何人採用するか」「どの部署でどのようなポジションを募集するか」といった具体的な数値目標や実行計画を示すものです。これに対し採用戦略は、企業の中長期的な経営ビジョンや事業計画に基づき、「どのような人材を、どのように採用していくか」という方針を定めるものです。
採用計画が具体的な採用活動の設計図だとすれば、採用戦略はその活動の指針となる羅針盤のような存在です。採用戦略があってこそ、採用計画は経営目標の実現に向けた効果的なツールとなります。
また、採用戦略は人材市場の動向や社会環境の変化も考慮して策定されるため、より広い視野で採用活動を展開することができます。
採用戦略のメリット

採用戦略を導入することで、企業は優秀な人材の確保から離職率の抑制、さらには採用業務の効率化まで、さまざまなメリットを得ることができます。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
優秀な人材を確保できる
採用戦略を立てることで、自社が求める優秀な人材を効率的に採用できるようになります。市場分析や競合他社との差別化、求職者のニーズ把握など、戦略的なアプローチにより、質の高い応募者を集めることが可能になります。
一方、採用戦略がない場合、「コストをかけても成果が出ない」「競合に良い人材を奪われる」「ミスマッチによる早期退職が増加する」といったリスクが高まります。また、長期的な人員計画が立てられないため、欠員が生じたときに既存社員の負担が増加し、さらなる離職を引き起こす悪循環に陥る可能性もあります。
離職率を抑えられる
採用戦略を立てる過程で、自社の強みや企業文化、求める人材像が明確になります。これにより、採用時のミスマッチを防ぎ、入社後の早期離職を抑制することができます。適切な採用戦略を立てることで、このような課題に対応することが可能です。
また、採用戦略には入社後のフォロー体制の整備も含まれるため、新入社員の定着率向上にも効果を発揮します。戦略的な採用活動により、企業と求職者の相互理解が深まり、長期的な雇用関係の構築につながります
採用業務の効率化と経費削減ができる
採用戦略に基づいて採用活動を進めることで、業務の効率化とコスト削減を実現できます。明確な戦略があれば、採用手法の選択や予算配分を適切に行え、無駄な採用コストを抑制できます。
また、進捗管理が容易になり、問題が発生した際も早期に対策を講じることができます。採用計画が遅れている場合でも、経営戦略と整合性のある判断が可能となり、場当たり的な対応を避けられます。
さらに、採用戦略は企業の方針や目標と連動しているため、各部門との連携がスムーズになり、採用業務全体の効率化にもつながります。結果として、採用にかかる時間とコストを最適化することができます。
採用戦略立案の手順

効果的な採用戦略を立案するには、段階的なアプローチが必要です。ここでは、採用戦略の立案から実行までの具体的な手順について解説します。
手順1:採用戦略立案チームを編成する
採用戦略は人事部門だけでなく、企業全体で取り組むべき重要課題です。そのため、経営層や事業部門の責任者など、会社全体の状況を把握している人材を含めたチームを編成することが重要です。
特に経営戦略との整合性を確保するため、経営陣の参画は不可欠です。また、実際に採用した人材が配属される現場の声を反映するため、各部門の責任者や若手社員など、多様な視点を持つメンバーを含めることで、より実効性の高い戦略を立案できます。
手順2:採用計画の策定
中長期的な経営計画や事業計画をもとに、必要な人材の質と量を具体化します。今後5〜10年間の事業展開を見据え、「いつまでに、どのような人材を、何人採用する必要があるか」を明確にします。
その際、部署ごとの人員体制や退職予定者の把握、新規事業計画なども考慮に入れます。また、内部での人材育成や配置転換の可能性も検討し、外部からの採用が必要な人数を適切に見積もります。
手順3:採用したい人物像を設定
採用したい人材像を具体化するため、ペルソナを設定します。年齢、性別、学歴、職歴、スキル、志向性など、できるだけ詳細に理想の候補者像を描きます。
特に重要なのは、必須条件(MUST)と歓迎条件(WANT)を明確に区別することです。また、応募者の価値観やキャリアプランなども考慮し、自社の企業文化との親和性も重視します。これにより、選考基準が明確になり、ミスマッチを防ぐことができます。
手順4:市場や競合、自社の分析
採用市場の動向、競合他社の採用状況、自社の強みと弱みを分析します。労働市場の需給バランスや求職者のニーズ、業界特有の採用課題などを把握し、効果的な採用戦略の立案につなげます。
特に自社の強みについては、企業理念や事業内容、職場環境、キャリア開発機会など、多角的な視点で分析することが重要です。これらの情報は、採用活動における差別化ポイントとなります。
3C分析
3C分析は、Customer(求職者)、Competitor(競合他社)、Company(自社)の3つの視点から採用市場を分析するフレームワークです。求職者のニーズや競合他社の採用状況を把握し、自社の強みを活かした採用戦略を立案する際に有効です。
たとえば、求職者が重視する要素や競合他社の採用手法を分析し、自社の差別化ポイントを見出すことができます。
SWOT分析
SWOT分析では、自社の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理します。
たとえば、強みとして「充実した研修制度」、弱みとして「知名度の低さ」、機会として「市場の成長性」、脅威として「競合の採用強化」などを挙げ、それぞれの要素を活かした採用戦略を策定します。
手順5:採用手法を選定する
採用ターゲットや予算に応じて、最適な採用手法を選定します。求人広告、人材紹介会社、リファラル採用、ダイレクトリクルーティングなど、各手法の特徴や効果を比較検討します。
一つの手法に限定せず、複数の手法を組み合わせることで、より広い層にアプローチすることができます。また、各手法のコストパフォーマンスを検証し、予算を効果的に配分することも重要です。
手順6:採用プロセスを設計する
応募者の選考から内定までの具体的なプロセスを設計します。書類選考、適性検査、面接など、各段階での評価基準や合格基準を明確にし、選考の一貫性を確保します。
ファネル分析を活用して、各段階での通過率を設定し、必要な応募者数を逆算します。また、面接官の選定や育成にも注力し、効果的な人物評価ができる体制を整えます。
手順7:採用スケジュールの設定
採用計画に基づき、具体的な実施スケジュールを策定します。募集開始から内定までの期間、各選考段階の所要期間、面接官の確保可能な日程などを考慮し、現実的なスケジュールを組みます。
また、競合他社の採用活動時期も考慮し、優秀な人材を確保しやすいタイミングを見極めることも重要です。
手順8:採用戦略の実行
策定した戦略に基づき、実際の採用活動を開始します。選考や面接を通じて、応募者の適性を見極めながら、自社の魅力も効果的に伝えていきます。
内定後は、入社までの期間のフォローを丁寧に行い、辞退を防ぎます。また、入社後も研修やメンター制度などを通じて、新入社員の早期戦力化と定着を支援します。
採用戦略のポイント

採用戦略を成功に導くためには、戦略の立案だけでなく、実行段階での取り組みも重要です。ここでは、採用戦略を効果的に進めるための重要なポイントについて解説します。
採用戦略を社内で共有する
採用戦略は、人事部門だけでなく企業全体で共有し、共通認識を持つことが重要です。なぜなら、採用活動は会社の未来を左右する重要な取り組みであり、全社的な協力体制が不可欠だからです。
採用戦略を社内で共有することで、各部署が求める人材像や採用の優先順位が明確になり、現場と人事部門の意識のズレを防ぐことができます。また、面接官の選定や入社後の教育体制の整備なども円滑に進められ、採用した人材の早期戦力化や定着率の向上にもつながります。
採用担当者のスキルを向上させる
優れた採用戦略があっても、それを実行する採用担当者のスキルが不足していては、期待する成果は得られません。特に面接では、応募者の能力や適性を正確に見極めるヒアリング力や、自社の魅力を効果的に伝えるコミュニケーション力が求められます。
また、昨今ではオンライン面接の普及やSNSを活用した採用活動など、採用手法も多様化しています。採用担当者は、これらの新しい手法にも対応できるよう、継続的なスキルアップが必要です。定期的な研修や面接官トレーニングを通じて、選考の質を高めることが重要です。
採用戦略後にやるべきこと

採用戦略を策定した後、それを効果的に活用し成功へ導くためには、継続的な改善とフォローが重要です。以下に、採用戦略後に実施すべきポイントを解説します。
定期的に効果の検証・改善を行う
採用戦略は、半期や年度ごとに効果を検証し、継続的に改善を図ることが重要です。応募者数、選考通過率、内定承諾率、採用コストなど、具体的な数値をもとにPDCAサイクルを回します。
また、期待した成果が得られない場合は、その原因を分析し、次の採用活動に活かすことが大切です。採用市場の動向や求職者のニーズは常に変化しているため、柔軟に戦略を見直し、適切な改善を加えることで、より効果的な採用活動を実現できます。
採用後のサポート
採用後のサポートは、人材の定着と戦力化を左右する重要な要素です。入社後の研修プログラムや、メンター制度の導入、定期的な1on1面談の実施など、新入社員が働きやすい環境を整備することが重要です。
特に入社直後は、業務面での不安や職場環境への適応に課題を感じやすい時期です。この時期に適切なサポートを提供することで、早期離職を防ぎ、スムーズな職場定着を促進できます。また、新入社員の成長をサポートすることで、組織全体の生産性向上にもつながります。
採用戦略を成功させた企業事例3選

採用戦略を効果的に実行し、優秀な人材の確保に成功している企業があります。ここでは、特徴的な採用戦略で成果を上げている3社の事例をご紹介します。
求人情報サイトの運用など人材サービスの大手A社
人材サービス大手のA社は、オウンドメディアを活用した情報発信の強化により、採用活動で大きな成果を上げています。同社は自社の採用オウンドメディアを運用し、A社で働く社員に焦点を当てた情報発信を積極的に行っています。
特徴的なのは、膨大な数の社員インタビューを職種別に掲載している点です。入社理由や働くやりがいなど、具体的な声を通じて企業文化や仕事の魅力を伝えることで、求職者の理解を深めています。
また、採用サイトでは長文のストーリーを通じて自社のミッションや価値観を丁寧に説明し、共感を得られる人材との接点を増やすことに成功しています。
大手自動車会社B社
大手自動車メーカーB社は、キャリア採用と第二新卒採用の強化により、多様な人材の確保に成功しています。特に注力しているのが、社員による紹介制度(リファラル採用)の推進です。
同社は社内の従業員による推薦システムを整備し、既存社員のネットワークを活用した人材獲得を行っています。また、経営陣の理念やビジョン、職場環境や業務内容に関する情報を自社メディアで積極的に発信し、企業の透明性と魅力向上に努めています。
さらに、各部門が直接採用活動を主導する現場主導型の採用を導入し、部門ごとの具体的なニーズに合った人材の確保を実現しています。
フリマアプリを運用する大手企業C社
IT企業のC社は、マルチメディア戦略を活用した技術力と企業文化の発信により、エンジニア採用で成果を上げています。同社は採用サイトでの基本情報の発信に加え、テックブログでの技術情報の共有、社員によるnoteでの企業文化や働き方の発信など、複数のメディアを効果的に活用しています。
特にエンジニア採用においては、開発環境や技術スタックの詳細な公開、技術的な意思決定プロセスの共有など、技術者が重視する情報を積極的に発信。
また、組織の透明性を重視し、失敗事例を含めた率直な情報共有を行うことで、求職者からの信頼獲得に成功しています。
まとめ
採用戦略は、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な要素です。人材獲得競争が激化し、求職者のニーズが多様化する現代において、戦略的な採用活動なしでは優秀な人材の確保は困難です。
適切な採用戦略を立案・実行することで、企業は効率的な人材確保を実現し、採用コストの削減と早期離職の防止を図ることができます。また、定期的な効果検証と改善を行うことで、より効果的な採用活動を展開し、企業の成長につなげることができます。