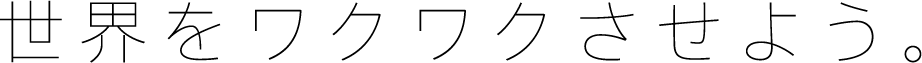「応募者が集まらない」「良い人材が採用できない」──。人手不足が深刻化する中、従来の求人広告だけでは思うような採用成果が得られないとお悩みの企業も多いのではないでしょうか。
実は今、多くの求職者は企業の理念や文化、働き方など、より詳しい情報を求めています。そんな求職者のニーズに応える手法として注目を集めているのが「採用広報」です。
本記事では、採用広報の基礎知識から具体的な実施手順、成功事例まで詳しく解説します。これを読めば、自社に合った採用広報戦略を立案し、優秀な人材の獲得につなげることができるでしょう。
採用広報とは

採用広報とは、企業が求職者に対して自社の魅力や働き方、企業文化などを積極的に発信し、優秀な人材を採用するための戦略的な広報活動です。従来の求人広告のように応募を待つ「待ちの採用」ではなく、企業から主体的に情報を発信する「攻めの採用」というアプローチが特徴です。
採用広報では、求人情報だけでなく、社員インタビューや職場の雰囲気、福利厚生、キャリアパスなど、入社後の働き方をイメージできる情報を様々な媒体を通じて発信します。そうすることで、求職者の企業理解を深め、応募意欲を高めることができます。
また、採用広報は人事部門だけでなく、広報部門や現場社員と連携して進めることが理想的です。人事部門が採用情報を整理し、広報部門が効果的な発信方法を検討、現場社員が実態に即した情報を提供するなど、全社的な取り組みとして展開することで、より効果的な採用活動が実現できます。
採用広報のメリット

採用広報を活用することで、企業は多くの利点を享受できます。以下では、企業ブランドの構築、質の高い応募者の獲得、採用活動の効率化という3つのポイントを中心に解説します。
企業ブランドの構築と認知度向上
採用広報を通じて企業の認知度を高め、魅力的な企業イメージを構築することができます。特にSNSやオウンドメディアを活用することで、企業の理念やビジョン、社風、働き方など、求人広告だけでは伝えきれない情報を効果的に発信できます。
また、転職を考えていない潜在層に対しても企業の存在や魅力を認知してもらうことで、将来的な転職のタイミングで選択肢として検討してもらえる可能性が高まります。さらに、企業の社会貢献活動や成長ストーリーなども発信することで、企業としての信頼性や好感度の向上にもつながります。
質の高い応募者の獲得
採用広報では、企業の価値観や事業内容、実際の働き方などを詳細に発信することで、自社に共感し、本当にマッチする人材からの応募を促すことができます。企業のリアルな姿を伝えることで、求職者は入社後の働き方やキャリアパスをより具体的にイメージでき、ミスマッチを防ぐことができます。
特に、社員インタビューや職場の雰囲気を伝えるコンテンツは、求職者の企業理解を深める効果があります。その結果、企業文化に共感し、長期的に活躍が期待できる人材の獲得につながります。
採用活動の効率化
採用広報によって企業の詳細な情報を事前に発信することで、選考プロセスがより効率的になります。求職者は企業についての理解が深まった状態で選考に臨むため、面接での質問もより本質的なものとなり、選考の質が向上します。
また、入社後のミスマッチを防ぐことで早期離職を抑制でき、採用コストの削減にもつながります。さらに、自社への直接応募が増えることでエージェント費用を抑えられるほか、内定承諾率の向上により、必要な採用人数を効率的に確保することが可能になります。
採用広報が注目される理由

近年、採用広報が注目されるのには、以下のような背景があります。
人材獲得競争の激化
深刻な人手不足が続く日本では、企業間の採用競争が一段と激化しています。総務省によると、生産年齢人口(15~64歳)は2020年の7,509万人から2040年には5,978万人、2065年には4,529万人まで減少すると予測されています。
このような状況下では、求人広告を掲載して応募を待つ「待ちの採用」だけでは、優秀な人材の確保が難しくなっています。企業は自社の強みや特徴を積極的に発信し、他社との差別化を図ることで、求職者から「選ばれる企業」になる必要があるのです。
参考:総務省「第1節 今後の日本社会におけるICTの役割に関する展望」
転職に対する意識の変化
近年、「一つの会社に長く勤める」という従来の価値観が大きく変化してきています。より良い労働条件を求めての転職や、新しい経験を得るためのキャリアチェンジを前向きに捉える人が増加しています。
こうした意識の変化により、現在は転職を考えていないものの、「良い機会があれば転職したい」と考える転職潜在層が増加しています。そのため企業は、転職活動を行っている顕在層だけでなく、将来的な採用を見据えて潜在層へのアプローチも重要になってきているのです。
デジタル化に情報発信が簡単になった
インターネットやSNSの普及により、企業が自社の情報を発信できる手段が格段に増えました。自社ホームページやブログ、SNSなど、さまざまな媒体を活用して企業の魅力を効果的に伝えることが可能になっています。
また、求職者も企業に対してより透明性の高い情報開示を求めるようになってきました。企業の理念や文化、実際の働き方など、求人広告では伝えきれない情報も、デジタルメディアを通じて積極的に発信することで、求職者との信頼関係を構築することができます。
効果的な採用広報戦略の立案手順

採用広報を成功させるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ただ漠然と情報発信を始めても、期待する効果は得られません。ここでは、採用広報を効果的に進めるための7つのステップをご紹介します。
採用広報の目的を明確にする
採用広報を始める前に、まずは現状の採用課題を明確にし、具体的な目標を設定することが重要です。「認知度の向上」「応募数の増加」「採用におけるミスマッチの低減」など、自社が抱える課題に応じて目的を定めましょう。
また、採用広報の目的は中長期的な経営計画や事業戦略と紐付けて考える必要があります。「どのような組織を目指すのか」「今後の事業展開に必要な人材は何か」といった視点から、採用広報の方向性を定めることが成功への近道となります。
ターゲット人材の明確化
採用広報のターゲットとなる人材像を具体的に設定します。必要なスキルや経験はもちろん、自社の理念や価値観に共感できる人物かどうかも重要な判断基準となります。
効果的なターゲティングのためには、ペルソナ設定が有効です。年齢、性別、キャリア、興味関心、情報収集方法など、できるだけ具体的な人物像を描き出しましょう。また、実在する社員の中から理想的な人材をモデルケースとして参考にすることで、より実践的なペルソナ設定が可能になります。
発信するメッセージ内容を整理する
自社の魅力や独自性を明確に言語化することが重要です。4P分析や3C分析を活用して、自社の強みを洗い出し、差別化要素を特定しましょう。
特に重要なのは、経営理念やビジョン、企業文化、働く環境、キャリアパスなど、求職者が重視する情報です。これらを「なぜ」「どのように」という視点を含めて整理し、説得力のあるメッセージとして構築していきます。
情報発信媒体を選択する
情報発信媒体は、オウンドメディア(自社サイト、ブログ)、アーンドメディア(SNS、口コミ)、ペイドメディア(求人広告、イベント)の3つに大別されます。
それぞれの特性を理解し、ターゲット人材の情報収集行動に合わせて最適な媒体を選択しましょう。例えば、若手層向けにはSNSが効果的である一方、専門職採用ではオウンドメディアでの詳細な情報発信が重要になります。
具体的なコンテンツを企画する
ターゲットや目的に応じて、効果的なコンテンツを企画します。代表的なものには、社員インタビュー、職場紹介動画、社内イベントレポート、キャリアストーリーなどがあります。
特に求職者の「リアル」を知りたいというニーズに応えるため、実際の社員の声や職場の雰囲気が伝わるコンテンツが効果的です。また、5W2Hのフレームワークを使って企画を具体化し、コンテンツの目的や期待する効果を明確にしましょう。
KPIを設定する
採用広報は、実施して終わりではありません。長期的な指標として「応募者数」「内定承諾率」「入社後の定着率」、短期的な指標として「記事PV数」「SNSエンゲージメント率」などが挙げられます。
定性的になりがちな採用広報の成果を、可能な限り定量的に測定できる指標を設定することで、PDCAサイクルを回しやすくなります。
実行とフィードバック
採用広報は一度始めたら終わりではありません。設定したKPIに基づいて定期的に効果を測定し、必要に応じて戦略の見直しを行うことが重要です。
データの分析やユーザーからのフィードバックを基に、発信内容や方法を継続的に改善していきましょう。また、社内からも積極的に意見を集め、より効果的な採用広報活動へとブラッシュアップしていきます。
採用広報の主な手法

採用広報には様々な手法があり、それぞれの特徴を活かして効果的に組み合わせることが重要です。ここでは、代表的な5つの手法について、その特徴とポイントをご紹介します。
オウンドメディアの活用
自社で運営するオウンドメディアは、採用広報の基盤となる重要な媒体です。自社サイトや採用ページでは、企業理念、事業内容、社員インタビュー、働き方など、詳細な情報を自由に発信することができます。
特に、求職者が深く知りたい「実際の仕事内容」「キャリアパス」「福利厚生」といった情報を、写真や動画も交えながら具体的に伝えることが可能です。また、Web上から直接エントリーできる応募フォームを設置することで、興味を持った求職者の行動を促すことができます。
SNSマーケティング
FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどのソーシャルメディアは、企業の日常的な活動や社風を気軽に発信できる媒体として効果的です。特に、社内イベントの様子や社員の声など、親近感のある情報発信が可能です。
SNSの強みは、求職者との双方向のコミュニケーションが取れる点です。コメントやダイレクトメッセージを通じて直接対話ができ、信頼関係を築きやすいのが特徴です。また、情報の拡散性が高く、転職潜在層への認知拡大も期待できます。
Wantedlyの活用
Wantedlyは、企業理念や価値観への共感でマッチングを図るビジネスSNSです。ミレニアル世代を中心に330万人以上が登録しており、求人募集だけでなく、企業のストーリーやブログ、イベント開催など多彩な採用広報活動が可能です。
サイトの特性上、意欲的な求職者が多く、特にスタートアップ企業やIT企業の採用で高い効果を発揮します。また、ターゲットに直接アプローチできるダイレクトリクルーティング機能も備えており、積極的な人材獲得が可能です。
note proの活用
note proは、企業の採用ブログやオウンドメディアとして活用できる法人向けサービスです。記事の作成や公開が簡単で、社員が個人アカウントで書いた記事を「マガジン」として法人アカウントにまとめることもできます。
メニューやサイトカラーなど自由なカスタマイズが可能で、企業ブランディングを意識した情報発信ができます。特に、社員の生の声や企業文化をストーリー性のある記事として発信できる点が強みです。
イベントの活用
合同説明会や採用イベントは、求職者と直接コミュニケーションを取れる貴重な機会です。企業の魅力を直接伝えられるだけでなく、求職者の生の声や反応を得られることで、採用戦略の改善にも活かせます。
近年ではオンラインイベントも増加しており、地理的な制約なく多くの求職者とコンタクトを取ることが可能になっています。また、イベントの様子を動画やブログで発信することで、参加できなかった求職者へのアプローチにも活用できます。
採用広報の最新トレンド

採用広報の手法は、テクノロジーの進化や求職者のニーズの変化に合わせて日々進化しています。特に注目を集めているのが、動画や音声を活用した新しい形の情報発信です。
動画コンテンツ
動画コンテンツは、文章や写真だけでは伝わりにくい企業の雰囲気や職場環境を視覚的に伝えられる効果的な手法として注目を集めています。
YouTubeでは社員インタビューや職場紹介、1日の業務の流れなど、詳細な情報を発信できる一方、TikTokでは若年層向けのショート動画で企業の魅力を端的に伝えることができます。動画には視覚・聴覚の両方に訴求できる強みがあり、求職者の印象に強く残りやすいという特徴があります。
音声メディア
PodcastやVoicyなどの音声メディアを活用した採用広報も増加しています。音声メディアの最大の特徴は、通勤中や家事の合間など「ながら聴き」が可能な点です。求職者は日常生活の中で自然に企業情報に触れることができます。
また、音声コンテンツは動画と比べて制作コストが低く、気軽に情報発信を始められるのも魅力です。社員の生の声や企業文化を自然な形で伝えられることから、より親近感のある採用広報が実現できます。特に、意欲的に情報収集を行う優秀層へのリーチに効果的とされています。
採用広報を行う際の注意点

採用広報は効果的な採用手法ですが、闇雲に始めても期待する成果は得られません。ここでは、採用広報を成功に導くために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。
中長期的に考える
採用広報は、短期的な効果を求めすぎないことが重要です。ペイドメディアでさえある程度の時間を要し、オウンドメディアやアーンドメディアの運用では、年単位の時間がかかるのが一般的です。
そのため、経営層と連携を図りながら、中長期的な視点で計画を立てることが欠かせません。例えば「〇年度中にエントリー数を□%アップさせる」といった具体的な目標を設定し、それに見合った予算と人員を確保することが大切です。短期的な成果を追い求めすぎると、途中で挫折してしまう可能性があります。
発信内容と現状に一貫性を持たせる
採用広報で発信する情報は、社内の実情と乖離がないよう注意が必要です。例えば、業務の特性上リモートワークが難しい状況であるにもかかわらず、柔軟な働き方を強調しすぎると、入社後のギャップによって早期離職を招く可能性があります。
また、複数の媒体で情報発信を行う場合も、一貫性のあるメッセージを心がけましょう。発信内容に矛盾があると、求職者の信頼を失うだけでなく、既存の従業員のモチベーション低下にもつながりかねません。
他部署の協力が必要
採用広報は、人事部門だけで完結する活動ではありません。社員インタビューや職場の様子の撮影、各部門の業務内容の紹介など、様々な場面で他部署の協力が不可欠です。
そのため、採用広報の目的や意義を全社で共有し、協力を得やすい体制を作ることが重要です。特に、実際の現場の声を発信することで、より説得力のある採用広報が実現できます。定期的な情報共有の機会を設けたり、協力してくれた社員への感謝を示したりすることで、社内の協力体制を強化しましょう。
採用広報の成功事例3選
採用広報を成功させている企業の取り組みを見ることは、自社の戦略立案にとって大きなヒントとなります。ここでは、特徴的な取り組みで成果を上げている3社の事例をご紹介します。
メディア・広告・ゲームなどの事業を展開するA社
大手IT企業のA社は、SNSを活用した採用広報で高い成果を上げています。特に新卒採用では、X(旧Twitter)に採用専用アカウントを開設し、採用活動のスタートやインターンシップ情報、イベント情報などを定期的に発信。2012年の開設以来、8,000人以上のフォロワーを獲得しています。
また、Instagramの新卒専用アカウントでは、選考情報や体験談、OB・OG訪問の様子など、就活生の知りたい情報を積極的に発信。採用活動開始前から企業への興味関心を高める取り組みに成功しています。
ECサイトを展開する大手企業B社
B社は、全国各地の拠点で働く社員にスポットを当てた採用広報を展開しています。企業ホームページやオウンドメディアでは、従業員の満足度や企業文化に関する評価を積極的に公開し、求職者からの信頼獲得に成功しています。
特に、各拠点で働く社員へのインタビューを丁寧に掲載することで、求職者が自分の希望する地域での働き方を具体的にイメージできる工夫を施しています。また、口コミサイトでは5,000件以上の社員の声が集まり、透明性の高い情報発信を実現しています。
クラウドサービスの開発・運営をするC社
C社は、採用ブログを活用した情報発信に力を入れています。新卒採用、中途採用それぞれに向けて、1ヶ月に3本以上のペースで採用広報記事を配信。社員の声や企業文化、働き方など、多角的な情報発信を行っています。
特にエンジニア採用においては、技術ブログを通じて社内の技術力の高さをアピール。社内勉強会のスライド共有や、技術選定の背景に関する詳細な解説など、専門性の高いコンテンツを発信することで、技術志向の高い人材の獲得に成功しています。
まとめ
採用広報は、企業が優秀な人材を確保するための重要な戦略となっています。人手不足が深刻化し、求職者のニーズも多様化する現代において、従来の求人広告だけでは十分な採用成果を得ることは困難です。
採用広報を戦略的に展開することで、企業の魅力を効果的に発信し、求職者との良好な関係を構築することができます。目的設定から実行、効果測定まで、計画的に取り組むことで、採用力の向上と採用コストの低減を実現することが可能です。